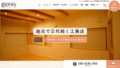貞観年間から続く由緒ある社
田蓑神社は、貞観11年(869年)に鎮座した大阪市西淀川区佃の鎮守様として、長い歴史を刻んできました。住吉三神と神功皇后を祀るこの社は、神功皇后が三韓征伐の帰途にこの地へ立ち寄られ、島の海士が白魚を献上した由来から始まっています。かつて田蓑嶋姫神社と称され、江戸時代には住吉神社と改名し、明治元年(1868年)に現在の社名となりました。神崎川と左門殿川の分岐点南方に位置する境内は、平安時代には天皇の即位儀礼である八十島祭の祭場であったと推定されており、古代から信仰の中心地として重要な役割を担ってきました。
長きにわたり地域の人々に親しまれる田蓑神社は、阪神本線「千船」駅より徒歩約15分の便利な立地にあります。境内には駐車場2台分のスペースを設け、いつでも参拝可能な開かれた環境を整えています。祈祷については事前予約制となっており、電話でのご連絡によりお受けしております。参拝や祈祷を通じて心を整える場として、幅広い世代の方々に信頼され続けています。
徳川家康公との深い縁が結ぶ歴史
天正年間、徳川家康公が多田神社へ参詣される際に田蓑嶋へ立ち寄られ、この地の漁民が神崎川の渡船を務めたことから、深い関わりが始まりました。家康公は漁民たちに全国での漁業権と税の免除を認める恩賞を与え、また「漁業の傍ら田も作れ」との命により、村名を田蓑から佃へと改めることとなりました。この時、田蓑の名を残すため神社名も住吉神社から田蓑神社へと改められています。寛永8年(1631年)には境内に徳川家康公を祀る東照宮が建立され、毎年5月17日には東照宮祭が営まれています。佃漁民と徳川家との強い絆を示す「佃漁民ゆかりの地」碑は、未来に残したい漁業漁村の歴史文化財産百選に選ばれ、その顕彰史跡としての価値が認められています。
天正18年(1590年)8月、家康公の関東下向の際には、佃の漁夫33人と田蓑神社宮司平岡正太夫の弟である権太夫好次が、分神霊を奉載して江戸へと向かいました。やがて幕府より鉄砲洲向かいの干潟を賜り築島し、故郷の名をとって佃島と定め、正保3年(1646年)6月29日に住吉三神、神功皇后、徳川家康の御神霊を奉遷祭祀して佃住吉神社を創建しました。この歴史的な縁により、大阪市西淀川区佃と東京都中央区佃は深い結びつきを持ち、現在も両地域の佃小学校が姉妹校として1965年から相互に訪問しあう交歓会を開催するなど、地域間交流が受け継がれています。
伝統を守り地域を結ぶ祭礼と活動
田蓑神社では、年間を通じて様々な祭礼が執り行われ、地域の絆を深める場となっています。田蓑神社最大の祭では、「こどもふとん太鼓」と称して田蓑神社氏子青年団の先導のもと、地域の子供たちによってふとん太鼓大小各1台が佃地区内を巡行し、要所で大阪締めを行っています。祭の当日には拝殿で巫女による御神楽を見ることができ、夜店も10軒余りが出店して賑わいを見せます。規模こそ大きくはありませんが、地域の人々が一体となって伝統を守り継ぐ姿が印象的です。田蓑和楽会の活動を通じて、世代を超えた交流が育まれています。
境内には貴重な文化財も数多く保存されています。本殿両脇に安置された狛犬は、元禄15年(1702年)に奉献されたもので、大阪府内で最も古い石造浪速狛犬とされています。花崗岩製で像高約50cmのこの狛犬は、江戸時代前期に突然完成形で大坂に出現した謎多き存在として、狛犬研究者からも注目を集めています。平成7年(1995年)1月17日の阪神・淡路大震災により、田蓑神社は社殿が傾き社務所が全壊するなど大きな被害を受けましたが、地域の人々の努力により復興を遂げ、現在も変わらず参拝者を迎え続けています。