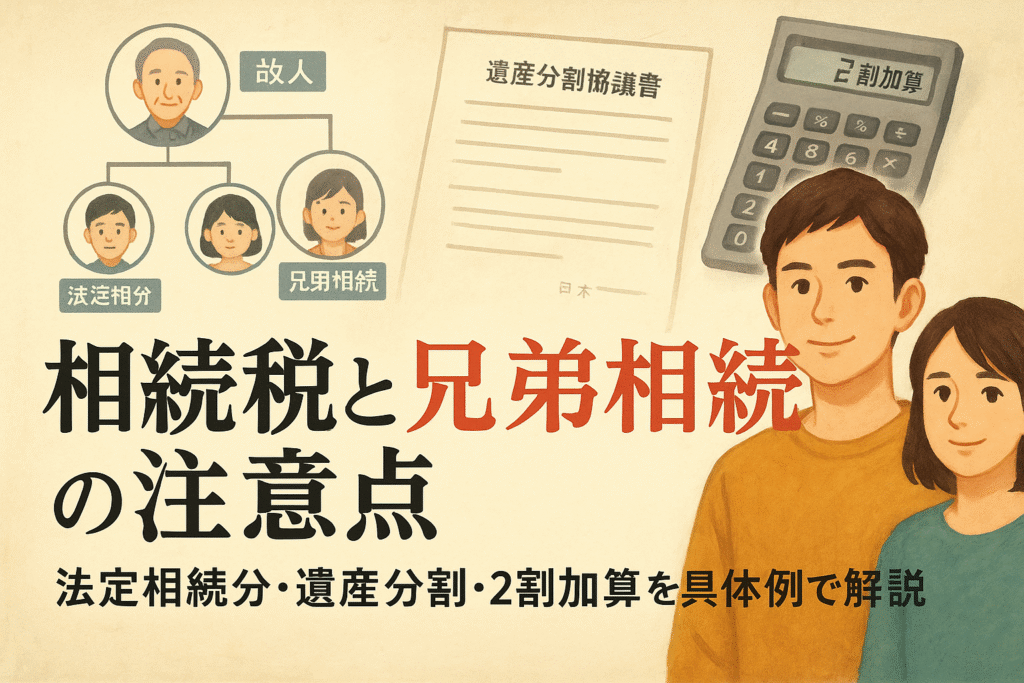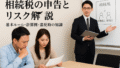「兄弟が遺産を相続する場合、他の親族よりも相続税が2割増しで課税されることをご存じでしょうか?相続税の仕組みや法定相続分は非常に複雑で、配偶者や子がいないと兄弟姉妹が相続人となり、そのパターンによって計算方法や手続きが大きく変わります。
『自分たちがどれくらい税金を負担するのか…』『複数人で分ける場合にトラブルにならないか不安…』そう感じている方も多いはずです。実際、相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」と法定相続人数により変動し、兄弟のみで相続する場合には控除額が想像以上に減ることも。
さらに、遺産分割協議がもつれると、納税や名義変更の遅延で余計な費用やペナルティが生じるリスクもあります。実務では手続きや必要書類も多岐にわたり、見落とすと申告期限を過ぎてしまうことも。
この特集では、兄弟が相続人となる具体的なケースから、法定相続分や相続税計算、実際の手続き・トラブル回避策まで一つひとつ体系立てて分かりやすく解説します。【2024年最新の公的基準】に基づいた信頼できる情報と、実務経験に基づく具体例を盛り込みました。
知らないまま放置すると、本来不要だったはずの負担が発生するかもしれません。ページを読み進めて、今のうちに正しい知識と備えを確かめておきましょう。
相続税における兄弟が関与するケースと法定相続分の基礎知識
兄弟が相続人となる法的根拠と具体的な状況 – 配偶者・子がいない場合や相続放棄の影響を解説
被相続人に配偶者や子供がいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。子供がすでに亡くなっている場合も、その子供(孫)が優先されますが、孫もいない場合、兄弟姉妹が相続人となる仕組みです。また、他の法定相続人が全員相続放棄したケースでも兄弟姉妹が相続人となります。独身で子供がいない兄弟が亡くなった際や、配偶者・子供のいない親族の遺産分割にも該当します。相続放棄があった場合、順位が繰り上がって兄弟姉妹や、その代襲となる甥や姪が相続人となることもあります。
主な兄弟が相続人となる場合の例:
-
配偶者・子がいない
-
子が全員先に死亡しており、孫もいない
-
他の相続人が相続放棄した
こうした場合、民法に基づき兄弟姉妹が相続人となることが明確に定められています。
法定相続分の基本ルールと兄弟間の分割割合 – 配偶者あり・なし、それぞれのケース別具体例
兄弟が相続する場合の法定相続分は民法で定められており、状況ごとに遺産の分け方が異なります。一般的な分割ルールは下記の通りです。
| 相続人の組合せ | 兄弟姉妹の相続分 | 配偶者の相続分 |
|---|---|---|
| 配偶者のみ、兄弟姉妹 | 1/4 | 3/4 |
| 兄弟姉妹のみ | 法定相続人で均等 | - |
例えば、兄弟3人だけが相続人の場合、それぞれの相続分は全て均等となり1/3ずつです。配偶者と兄弟姉妹がいる場合は、配偶者が3/4、残りの1/4を兄弟姉妹で分けます。相続人4人の兄弟姉妹の場合は、それぞれ1/4の取り分です。
分割割合の具体例:
-
兄弟2人のみの場合:各自1/2
-
兄弟3人の場合:各自1/3
-
兄弟4人の場合:各自1/4
このように法定相続分は人数によって自動的に算出されます。分割での揉めごとを避けるため、事前に計算式を確認しましょう。
兄弟姉妹・甥姪の相続権の範囲と代襲相続のルール – 兄弟相続特有のポイントを詳細に整理
兄弟姉妹が既に亡くなっている場合、その子にあたる甥や姪が「代襲相続人」となり、相続分を引き継ぎます。ただし、代襲相続が認められるのは一世代限りで、甥姪の子には権利が及びません。このため兄弟姉妹が存命ならその者が優先され、亡くなっていた場合、代襲相続で甥や姪が取得します。
主なポイントとしては次の通りです。
-
兄弟姉妹が亡くなっているときは甥姪が代襲相続する
-
甥姪の子や孫は代襲できない
-
配偶者や子供がいるケースでは兄弟姉妹・甥姪は原則相続人にならない
兄弟姉妹・甥姪の相続権まとめ表
| 相続状況 | 主な取得者 |
|---|---|
| 兄弟姉妹存命 | 兄弟姉妹 |
| 兄弟姉妹死亡・子あり | 甥姪(1世代限り) |
| 兄弟姉妹死亡・子なし | その相続分は他の兄弟または甥姪で分配 |
兄弟が相続人となる場合は、こうした法定相続分や代襲相続のルールを正しく理解しておくことが重要です。
相続税で兄弟間の相続税計算と2割加算ルールの詳細解説
兄弟相続に適用される相続税の2割加算の仕組みと課税対象者の具体的範囲
相続税は、被相続人の兄弟や姉妹が財産を取得した場合、2割加算のルールが適用されます。これは、直系卑属でない相続人や甥・姪などが該当します。つまり、配偶者や子ども以外の相続人が財産を受け取る際、通常の相続税額に20%上乗せされた金額を納付する必要があります。
2割加算の対象となる主な相続人は次の通りです。
-
兄弟姉妹およびその代襲相続人(甥・姪)
-
祖父母や親戚など直系尊属でない場合
この仕組みは、血縁の近い相続人よりも遠い相続人の税負担を大きくし、公平性を保つために設けられています。
相続税計算の基本手順と兄弟固有の計算上の注意点 – 基礎控除・課税遺産総額の具体的な算出方法
相続税の計算は、次の基本手順を踏みます。
- 相続財産総額を算出(不動産や預金、生命保険なども含む)
- 債務・葬式費用などを控除
- 基礎控除額を差し引く(3,000万円+600万円×法定相続人の数)
兄弟のみが相続人の場合、たとえば兄弟3人なら基礎控除額は4,800万円となります。
控除後の金額が課税対象です。さらに兄弟相続の場合、請求できる法定相続分は子の半分に相当します。相続税の計算例や早見表を使うことで実際の税額を把握しやすくなります。
兄弟が複数いる場合、それぞれの取得割合に応じて税額を計算し、最後に2割加算を適用します。
兄弟の人数別・遺産額別シミュレーション – 2人・3人・4人の場合の相続税負担比較と早見表活用方法
兄弟の相続人数や遺産総額によって、相続税額には大きな違いがあります。たとえば以下のケースを比較します。
| 兄弟人数 | 遺産総額 | 基礎控除額 | 課税遺産総額 | 法定相続分(1人あたり) | 2割加算後の相続税額(目安) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2人 | 6,000万円 | 4,200万円 | 1,800万円 | 1/2 | 税率適用後+20% |
| 3人 | 6,000万円 | 4,800万円 | 1,200万円 | 1/3 | 税率適用後+20% |
| 4人 | 6,000万円 | 5,400万円 | 600万円 | 1/4 | 税率適用後+20% |
実際の税率は課税遺産総額や取得額により変動しますが、兄弟の人数が多いほど1人あたりの負担は減少します。
早見表やシミュレーションツールを活用することで、自身のケースでの正確な相続税を確認できます。
兄弟のみの相続だと法定相続割合や控除額の影響も大きくなるため、早めに手続きやシミュレーションを行いましょう。
相続税における基礎控除と小規模宅地等の特例について兄弟に焦点を当てて解説
兄弟のみが法定相続人の場合の基礎控除計算方法 – 法定相続人の数による控除額の根拠と計算例
相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」と定められています。兄弟のみが相続人の場合、子供や配偶者がいないケースとなりますので、この式を正確に適用することが重要です。たとえば兄弟二人で相続人となる場合、基礎控除額は4,200万円(3,000万円+600万円×2)となります。兄弟三人では4,800万円、四人の場合は5,400万円です。この基礎控除を超える遺産に対して相続税が課税され、超過分が各相続人の法定相続分に応じて分配されます。また、兄弟が相続人の場合は相続税額に2割加算が行われる点もあわせて注意が必要です。
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 | 2割加算対象 |
|---|---|---|
| 1人 | 3,600万円 | 〇 |
| 2人 | 4,200万円 | 〇 |
| 3人 | 4,800万円 | 〇 |
| 4人 | 5,400万円 | 〇 |
兄弟が適用可能な相続税の各種特例 – 小規模宅地等の特例、相次相続控除の要件と適用範囲を丁寧に解説
兄弟が法定相続人の場合でも「小規模宅地等の特例」や「相次相続控除」が適用できるケースがあります。小規模宅地等の特例は現居住用や事業用の宅地を評価額の最大80%減額で計算できる制度ですが、兄弟には居住要件や生計同一要件を厳密に満たす必要があります。たとえば、被相続人と同居し家計も共にしていた兄弟であれば、特例の対象となることが可能です。また、相次相続控除は短期間で連続して相続が発生し、相続税が二重に発生する場合に税額を減額できる制度です。実際に短期間で兄弟間の相続が繰り返されたとき、この特例で負担を軽減できます。ただし、いずれも要件を満たすか必ず確認し、書類等の準備が重要です。
| 特例名 | 概要 | 兄弟適用ポイント |
|---|---|---|
| 小規模宅地等の特例 | 宅地評価額80%減額 | 同居・生計同一等厳しい条件。満たせば適用可能 |
| 相次相続控除 | 10年以内に再相続で税負担減額 | 兄弟への連続相続にも適用。ただし期間・条件に注意 |
相続税が非課税となる財産の種類とその活用 – 生命保険の非課税枠や特定の相続財産を区別して説明
相続税には課税対象外となる財産もあります。特に生命保険金には非課税枠があり、「500万円×法定相続人の数」まで非課税で受け取ることができます。たとえば兄弟が二人の場合、1,000万円までの死亡保険金が非課税となります。さらに、墓地や仏壇、公共団体への寄付金、不動産の登記費用なども相続税の課税対象から除外されます。これら非課税財産を活用することで、納税負担を減らすことが可能です。受け取った財産が非課税かどうかは、相続税申告前によく確認しましょう。
| 非課税財産 | 非課税限度額・内容 | 活用ポイント |
|---|---|---|
| 生命保険金 | 500万円×法定相続人の数まで | 所得控除で現金の相続税対策に有効 |
| 墓地・仏壇・仏具 | 制限なし | 財産計上不要 |
| 公共団体等への寄付金 | 相当額すべて | 寄付証明等を準備 |
兄弟間の相続税を含む遺産分割協議と代表的な分割方法の深堀り
現物分割・換価分割・代償分割・共有分割の特徴と兄弟間での適用事例
遺産分割には様々な方法があり、兄弟が相続人となる場合でも最適な分割方法を選択することが重要です。代表的な分割方法は次の4つです。
| 分割方法 | 特徴 | 兄弟間での適用事例 |
|---|---|---|
| 現物分割 | 財産そのものをそのまま取得 | 不動産を兄、預貯金を弟が取得 |
| 換価分割 | 財産を売却し現金で分ける | 不動産を売却して、現金を兄弟で折半 |
| 代償分割 | 一部の相続人が財産を取得し、他の相続人に金銭等で調整する | 長男が不動産取得、他の兄弟に現金で支払う |
| 共有分割 | 複数人で共同名義にする | 不動産を兄弟3人の共有名義とする |
現物分割は実物財産をそのまま分けるためトラブルが少なく、換価分割は現金化して平等に分配できるメリットがあります。代償分割や共有分割は調整や将来的な処分も考慮する必要があります。
兄弟間で起こりやすい遺産分割トラブルの実例と回避策 – 協議の進め方・話し合いのポイント
相続で兄弟間に多いトラブルには次のようなケースが見られます。
-
一部の兄弟が遺産の内容や金額に納得しない
-
連絡が取れない兄弟がいるため協議が進まない
-
共有名義のまま放置して将来の処分時に意見が割れる
これらを回避するためのポイントは次の通りです。
- 遺産のリストを全員で確認し、財産評価を明確にする
- 早期に協議を始め、合意内容は必ず書面に残す
- 可能な限り第三者(税理士や専門家)に同席してもらう
- 感情的にならず、冷静に事実にもとづいて話し合う
しっかりした情報共有と手順を踏むことでトラブルの予防につながります。
遺産分割調停・審判の流れと利用条件 – 話し合いが進まない場合の法的手続き詳細
兄弟間の協議がどうしてもまとまらない場合は、家庭裁判所での遺産分割調停や審判という法的手続きを利用することになります。
| 手続き | 概要 | ポイント |
|---|---|---|
| 調停申立て | 家庭裁判所を通じて話し合いを進める | 合意を目指す手続き、費用は比較的低額 |
| 調停不成立・審判 | 調停で合意できない場合に裁判所が間に入る決定をする | 裁判所が遺産分割内容を決定し、強制力が生じる |
調停手続きは全員の合意を目指しますが、不成立の場合は裁判所が分割内容を決定します。利用条件として、協議が著しく困難な状況や一部の相続人と連絡がつかない場合に選択します。遺産分割調停・審判はいずれも事前準備と専門知識が求められるため、利用時は専門家への相談をおすすめします。
相続税申告・納税の手続きと期限管理を兄弟の事例で徹底解説
兄弟相続で必要となる申告手続きの流れと申告期限内の正確な対応
兄弟が相続人となった場合の相続税申告は、他の親族よりも注意点が多いです。特に兄弟の場合、相続税が2割加算される点が特徴です。申告手続きは「被相続人が亡くなった日」の翌日から10か月以内に行う必要があり、この期限を超えると延滞税や加算税が発生するため厳守が不可欠です。申告の流れを整理すると、まず相続人全員で遺産の全容を把握し、各自の相続分を確定。そのうえで以下の手続きに進みます。
-
相続財産・債務の一覧作成
-
法定相続人の確定
-
遺産分割協議の実施
-
相続税申告書の作成と提出
-
税金の納付
兄弟のみが相続人となる場合、基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。相続税額早見表を活用して納税額を見積もると、申告準備に役立ちます。配偶者や子どもがいない場合、兄弟間の遺産分割内容もポイントです。
申告書類準備・戸籍謄本等収集のプロセスと特有の注意事項
申告手続きの準備でまず重要となるのが戸籍謄本や住民票などの書類収集です。兄弟の相続では被相続人との関係を遡るため、出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要となり、通常の子や配偶者より煩雑になります。必要書類の一覧を確認しましょう。
| 書類名 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 戸籍謄本一式 | 被相続人の出生から死亡まで | 抜けや誤りがないか事前に全て取得 |
| 住民票除票 | 被相続人・相続人用 | 必須書類のため早めの取得が安心 |
| 財産関連資料 | 不動産登記簿、預金通帳、保険証券等 | 全財産・債務の網羅的な確認が大切 |
兄弟が複数(2人・3人・4人など)いる場合は、それぞれの戸籍を全て揃える必要があり、相続人認定にも時間がかかる場合があります。加えて、代襲相続が発生する場合は甥姪の戸籍収集も必要です。申告期限に余裕を持って、専門家への早期相談がおすすめです。
相続税の納付方法と払えない場合の延納、物納制度の活用方法について解説
相続税の納付は、原則として現金一括納付がルールです。しかし、遺産に不動産が多い・現金化しにくい場合など、納付資金が不足するケースもあります。その際に活用できるのが延納・物納制度です。延納は、一定の条件を満たせば最長20年の分割払いが可能。物納は現金でも延納でも納付困難な場合、不動産などの財産で納付する仕組みです。
| 納付手段 | 概要 | 主な条件 |
|---|---|---|
| 一括納付 | 期限までに金融機関や税務署へ現金納付 | 申告期限(死亡の翌日から10か月以内)厳守 |
| 延納 | 5万円超の税金を年数分割で納付 | 担保や利子が必要、申告期限内に申請 |
| 物納 | 不動産・有価証券等で納付 | 延納も困難な時のみ、国が認めた財産で条件を満たす場合のみ |
これらの特例を利用するためには、厳格な審査やスケジュール管理が求められるため、早めに準備し申告時に同時提出が必要です。相続税の申告・納税は兄弟相続特有の複雑さがあるため、手続きの流れを理解し、確実な対応を進めていきましょう。
不動産・預貯金・有価証券の相続手続きと名義変更を兄弟で行う際の具体的実務
不動産相続時の登記手続きと費用相場 – 兄弟間での名義変更実務解説
不動産を兄弟間で相続する場合、まず遺産分割協議書の作成が必要です。協議書とともに故人の戸籍謄本や兄弟全員の戸籍謄本、固定資産評価証明書などを集め、相続登記申請を法務局へ行います。不動産の相続登記費用は登録免許税が評価額の0.4%、さらに司法書士に依頼する場合は別途5〜10万円前後が相場です。
| 必要書類 | 内容 |
|---|---|
| 遺産分割協議書 | 相続人全員の署名・実印が必要 |
| 被相続人の戸籍謄本一式 | 死亡記載のあるもの |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 続柄証明用 |
| 不動産の固定資産評価証明書 | 登録免許税算出に必要 |
| 印鑑証明書 | 相続人全員分 |
兄弟のみが相続人の場合、相続分は基本的に均等ですが、事前に分配比率や利用意向を話し合うことで後々のトラブルを防ぎやすくなります。
預貯金・有価証券の払い出し手続きの流れと必要書類の詳細
兄弟で預貯金や有価証券を分割する場合、各金融機関へ相続手続きを申し出ます。まず口座の凍結解除、相続人確定のための戸籍提出、遺産分割協議書の提示が必要です。金融資産の場合は財産評価日を確認し、取引証明や評価額証明も取得します。手続きごとに必要な書類が微妙に異なるため、事前確認が欠かせません。
| 資産区分 | 主な手続き手順 | 必要書類(一例) |
|---|---|---|
| 預貯金 | 口座凍結→相続人確定→払い戻し請求 | 戸籍謄本・協議書・印鑑証明 |
| 有価証券 | 証券会社に通知→凍結→名義書換・売却申請 | 戸籍謄本・協議書・取引明細 |
口座ごとに扱いが異なるため、複数の金融機関を利用していた場合はそれぞれで必要書類をそろえることが重要です。払い出し前に正確な相続分計算と意思確認を行いましょう。
兄弟間の実務上紛争を防ぐためのポイント – 書類管理と手続きの透明化
兄弟での相続では、感情や価値観の違いから思わぬ紛争が発生することがあります。書類や財産目録を全員に共有し、手続き状況を随時オープンにすることが信頼関係の維持に不可欠です。
-
相続人ごとに財産一覧表を共有
-
手続きの進捗や入出金履歴をこまめに報告
-
重要書類のコピーを全員が保有
もし話し合いが難航する場合は、専門家である税理士や司法書士を交えて第三者の意見を取り入れる方法が有効です。文書による同意や証拠の保存も将来的なトラブル抑制に役立ちます。円滑な相続実務のためには、透明性ある進行と信頼を大事にしたコミュニケーションが重要です。
相続税兄弟に関するよくある疑問と回答をQ&A形式で網羅
兄弟が相続人の時の相続税はいくらまで無税になるのか?
兄弟のみが相続人となる場合、相続税の非課税枠は「基礎控除額」により決まります。基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算されます。たとえば兄弟2人の場合は4,200万円、3人の場合は4,800万円が控除されます。遺産総額が基礎控除額以内であれば、相続税は発生しません。また、兄弟が法定相続人の場合は「2割加算」が適用され、相続税が他の続柄より多くなる点に注意が必要です。兄弟3人ならば4,800万円までが無税の一例です。
| 相続人の数 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
兄弟が複数人いる場合の遺産分割と税額計算の具体的違い
兄弟が複数いると遺産分割や相続税の計算が複雑になります。遺産は原則として均等に分割されますが、それぞれが取得する遺産額に応じて相続税を計算し、2割加算も適用されます。兄弟が3人の場合、それぞれが1/3ずつ遺産を受け取り、各自の相続税額も個別に算定します。法定相続分での分割例と計算方法は下記の通りです。
| 兄弟人数 | 一人あたりの相続分 | 基礎控除超過後の課税対象額から2割加算後に税率適用 |
|---|---|---|
| 2人 | 1/2 | 遺産総額を2等分して各自で計算 |
| 3人 | 1/3 | 遺産総額を3等分して各自で計算 |
| 4人 | 1/4 | 遺産総額を4等分して各自で計算 |
独身兄弟が亡くなった場合の相続手続きと問題点
独身の兄弟が亡くなったときは、子供や配偶者がいないため両親や兄弟姉妹が相続人となります。両親がすでに亡くなっている場合は兄弟のみが相続人です。兄弟が先に死亡している場合は、その子ども(甥や姪)が代襲相続人となるケースもあります。独身兄弟が亡くなったときの主な手続きは以下の通りです。
-
相続人調査(戸籍の取得と確認)
-
遺言書の有無の確認
-
遺産の分割協議
-
不動産や預貯金の名義変更
-
相続税の申告と納付
複数の兄弟や甥姪が関与する場合、協議が長引きやすいこと、相続人の確定に時間がかかる点に注意しましょう。
兄弟間の揉め事を防ぐためにできることは?具体的な実例紹介
兄弟間での遺産分割では意見が分かれることが多く、金銭的なトラブルの他、感情的な対立も生じやすいものです。よくある揉め事の原因と、その対策をリスト形式でまとめます。
-
強調ポイント:明確な遺言書作成、定期的な家族会議の実施
-
実例:不動産をどちらか一方が取得し、現金で調整することで争いを未然に防いだケース
-
プロの税理士や弁護士に相談して分割方法を第三者に委ねるのも有効
これらの対策を講じておくことで、兄弟間の不信感や対立を抑えることができ、スムーズな手続きが可能となります。
申告期限を過ぎてしまった時の対応策とリスク
相続税の申告期限は「被相続人の死亡を知った日の翌日から10カ月以内」です。この期限を過ぎると延滞税や加算税、さらには追徴課税が課される可能性があります。期限を過ぎてしまった際の対応策は下記の通りです。
- 速やかに税務署へ相談し、事情説明を行う
- 必要書類を揃え、早急に相続税申告書を提出する
- 延滞税や加算税が発生する場合、納付計画を立てる
ポイント
遺産分割が未了でも、ひとまず申告は必要なので注意してください。手続きの遅れは金銭的負担を増やす原因となるため、申告期限をしっかり守ることが重要です。
相続税兄弟での負担軽減対策と有効な節税ポイントを総まとめ
生前贈与や贈与税の活用による相続税の圧縮方法
兄弟が相続人になる場合、相続税は2割加算されるため、早い段階からの負担軽減策が重要です。特に生前贈与を上手に活用することで、相続財産を減らし、将来の税負担を下げることが可能です。例えば、「年間110万円までの贈与税非課税枠」や、教育資金の一括贈与非課税制度、結婚・子育て資金の非課税制度など、法定の非課税枠内で分散して財産移転を進めるのが有効です。
また、複数年にわたり計画的に贈与を実施すれば、累積財産の圧縮が期待できます。ただし、名義預金など形式だけの贈与は認められないため、贈与契約書の作成や、贈与事実を証明できる形で手続きを行うことが大切です。
主な生前贈与のポイント:
-
年110万円以下の贈与で非課税
-
教育・結婚資金の特例も活用
-
証拠書類の保管が不可欠
小規模宅地の特例を活用した不動産評価額の減額戦略
兄弟が相続人の場合も「小規模宅地等の特例」が適用できる場合があります。この特例を活用すれば、相続税評価額を最大80%減額することが可能です。対象となるのは、故人が居住していた宅地や事業用地などで、一定の要件を満たす必要があります。
特例適用には、「亡くなった方と同居」や「特定事業の継続」などの条件があり、兄弟のみで相続する場合は、同居していた相続人がいれば恩恵を受けられますが、登記や同居の事実など細かい点の確認が求められます。
| 特例種類 | 減額割合 | 適用要件 |
|---|---|---|
| 居住用宅地 | 最大80% | 同居・居住要件 |
| 事業用宅地 | 最大80% | 事業継続を相続人が行う |
この特例の活用可否はケースごとに異なるため、早期に適用条件を確認し、必要手続きを進めておくと安心です。
専門家の活用法と相談のタイミング – 税理士・司法書士の選び方と役割
相続税の早見表や計算シミュレーションを用いても、兄弟間の遺産分割や2割加算の適用基準は専門知識が不可欠です。トラブルを未然に防ぎ適切な申告を行うためにも、相続税に強い税理士への相談は必須です。税務申告はもちろん、例えば独身兄弟が死亡した場合の基礎控除額や、特例適用の判断、必要書類の用意など、専門家ならではのサポートを受けられます。
司法書士は不動産登記や遺産分割協議書の作成など法務手続きを担当しますので、各専門家の役割を整理することが大切です。
-
税理士:相続税申告、節税アドバイス、シミュレーション
-
司法書士:登記変更、法定相続情報一覧作成、協議書対応
信頼できる専門家選びは口コミや実績、専門性の高い分野での経験などを参考にすると失敗が少なくなります。早めに相談しておくことで安心して相続手続きが進められます。